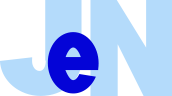Login
法律相談&トラブル情報
-業界の商取に関する法律相談 及び 善意の第3者への被害を防ぐための情報コーナー
検索サイト会員様向けに新しいサービス開始!
商取引に関する疑問に、JEN顧問弁護士からアドバイス!!
JEN検索サイトのご利用ありがとうございます。
このページは会員皆様がビジネス上のトラブルになるべく巻き込まれないための日頃注意する事と不幸にもトラブルに巻き込まれた場合の対応を中心にした「善意の第3者」のためのQ(Question) & A(answer and advice)ページです。
尚、下記内容に関しては、業界の商習慣を含めて一般論を個人的に記述したものです。個々の問題は個別に最寄の弁護士とご相談ください。
所有権留保付きで売買された建設機械の買受人についての即時取得
当社は、建設機械の製造販売業をしております。
当社は、Aに対し、パワーショベルを所有権留保特約付きで製造販売し、納品しました。
まだ代金が完済されていないのに、一般土木・橋梁工事等業を営むB社が本件物件を占有し使用していました。
B社は、建設機械の販売代理店と称する C 社を通じて Aから購入したと主張しています。
パワーショベルを取り戻せるでしょうか(参考裁判例:東京高判平成8年12月11日)
以前の Q & A で「善意の第三者」についてご説明させて頂きましたが、あなたの会社がパワーショベルを取り戻せる
か否かは、業者Bが「善意の第三者」にあたるか否かによって判断されることになります。
上記参考裁判例では、買主は、土木工事業者で橋梁工事や各種道路工事等の営業活動を行っているのであるから、
パワーシャベルのような高額な建設機械は、譲渡証明書が交付されることが慣例となっていることを十分認識してい
ると推測できるとし、買主の代表者は、売主や販売代理店とは取引も面識もなく、代金を完済したか確認していない
こと、販売代理店が何処のメーカーの販売代理店かを確認していないこと(実際には、建設機械の販売代理店ではあ
りませんでした。)売主とも一度も会わなかったことなど誰が売主であるかを正確に確認しようとしなかった言わざ
るを得ないことを理由に過失があった、すなわち、「善意の第三者」にはあたらないと判断しました。
本問の場合ですが、譲渡証明書について種々議論があり、裁判例も分かれているので譲渡証明書の有無だけでは決め
手にはなりません。しかし、パワーシャベルが一般的に高額であることに鑑みますと、外見上も新品と思われるよう
な場合には、代金が完済されているか否かにつき疑念を持ち、売主である A に対し代金完済の有無を確認する必要
があると思われます。
したがいまして、あなたの会社が本件パワーシャベルを購入するときにおいて、疑念を抱くような事情があったか
否か、その疑念を払拭するために何らかの確認をしたかどうかによって判断が分かれることになります。
中古の建設機械を購入した際に、時々盗難品や製造会社の所有権留保付き機械であることがあります。
そのような場合、「善意の第三者」であれば、当該機械を元の所有者に返却しなくても良いという話しを
聞きますが、「善意の第三者」とは何でしょうか。
正確には、元の所有者との関係では「第三者」である購入者が「善意かつ無過失」であれば、当該機械の所有権を取
得する場合があるということです。「善意」とか「悪意」とかいう言葉を使いますが、これらは勧善懲悪の善や悪の
ことではなく、他人の所有物であることを「知らないこと」を「善意」といい、他人の所有物であることを「知って
いること」を「悪意」といいます。そして、他人の所有物であることを「知らない」場合であっても、注意すれば他
人の所有物であることが分かった場合、すなわち「落ち度」がある場合を「過失」といい、注意を怠らなかった場合
すなわち「落ち度がなかった」場合を「無過失」といいます。したがいまして、「善意かつ無過失」とは、「他人の
所有物であることを知らず、知らないことにつき落ち度がないこと」をいいます。そして、「落ち度」があったか否か
は、具体的な取引の事情にもよりますので、このQ&Aの中で順次ご紹介していきたいと思いますが、日頃から真面
目に商売をしていれば、「善意かつ無過失」である場合がほとんどではないでしょうか。但し、「善意かつ無過失」
であっても、盗難又は遺失の時から2年間は、元の所有者に返還請求権が認められていることには注意が必要です。
中古品を売買するには「古物商」の許可を受ける必要があるのはどうしてですか?
盗難品や遺失物が中古品として取引されて窃盗などの犯罪が増える恐れがあるからです。それを防止し、その 被害を早く回復するために以下の規制があります。
◯ 古物商の登録をすること
建設機械を含め、中古商品のほとんどは「古物」に該当し、古物営業を行うためには営業所(営業所がない場合は
住所または居所)が所在する都道府県ごとに各公安委員会の許可を受けなければなりません。
◯ 古物商が守らなければいけないこと
10000円以上の物を売買するときは、買受する相手の身元確認が必要です。必ず相手の住所、氏名、連絡方法(TEL NO等)、取引のモデル、号機が記入された請求書。
現金支払いの場合➀ 領収書。初取引の相手の場合は、できれば ➁ 売買契約書もそろえて保管しデジタルで
データを記録してください(3年間保管)。
✣ 古物台帳の記入指導は各都道府県で少し違う様です。所轄の公安委員会にご相談ください。
(GOOGLE検索→都道府県公安委員会リンク集)
◯ 普段、古物取引で注意する事って?
➀ 値段
商売は誰でも安く買って高く売りたいですよね、でもあまり安いものには要注意!
特に機械の所有者の確認を心がけましょう。
➁ 取引相手の信用度
常日頃、業者間の評判を聞くようにしましょう。いかがわしい機械はいかがわしい業者に出回りやすいもの
です。特に初めての取引相手には要注意。信用できる人の紹介(メーカー担当者、ローン会社
担当者)で初めての取引の場合、その担当者から取引の情報をできるだけ詳しく聞いておいた方がよいで
しょう。(まるで紹介者や取引相手を信用していない様で言いにくいとは思いますが、ケースバイケースで.)
➂ 書類
✣ 請求書【絶対必要】:必ず相手の住所、氏名、連絡先が記入されたもの。
✣ 銀行振り込み証、現金の場合は領収書(どちらかは必須)
✣ 請求書、領収書がない商売は絶対やめましょう!
税務上の問題だけではなく、反社会的な資金洗浄(マネーロンダリング)の可能性もあります。
➃ 譲渡証明書
譲渡証明書といえば普通、自動車の名義変更等に使う[第21号様式](※1)を思い浮かべる人がほとんどか
と思いますが、建設機械には、日本建設機械工業会が発行した「統一譲渡証明書」(※2)という別の様式の
ものがあります。建設機械の場合、登録制ではなく、販売方法が多岐にわたる等の事もあって、その普及率は
残念ながら中古建機全体の数パーセントにもなりません。
しかし、製造年式の新しい中古機械は国内で流通することが多く、販売時に小売業者、ローン会社。
リース会社から譲渡証明書を要求されることも多々ありますので、年式の新しい機械を扱う場合はできるだけ入手しておくのが無難でしょう。
(※1譲渡証明書[第21号様式])
(※2(統一)譲渡証明書はメーカーから直接購入した「第一譲渡人」にしか発行されません。購入者から取り寄せましょう)
➄ 残債の可能性
エンドユーザーが一時的な資金繰りのために[残債]月の機械を売りに出すことがあります。
製造販売から5年以内の新しい機械は「残債」の可能性を考慮しましょう。
古い機械を中古機械ローンで購入している場合は残債のチェックが非常に難しくなります。
➅ 所有権を明示するシール
ローン中の機械は、ローン会社、リース会社の所有権を表すシールなどを機械の目立つところに貼ってその[所
有権]を明示するのが普通ですが、ローン・リース会社によってはエンジンカバー等の目立たないところに
貼っている場合があります。中には全く管理をしていないローン・リース会社もありますが万が一のトラブル
回避のためにも明示してあるものを発見したら所有者を確認してシールなどを写真データで残しておくといい
でしょう。

* 盗難情報・トラブル情報の掲載について
記載においては、被害届等の公的証明書をお願いする場合があります。
(2) JENは、誹謗中傷を防ぐための管理はいたしますが、各事案において裏づけ調査をしたわけでなく、記載内容の一切の責任は
投稿者にあります。(*記載は当社のフォームにて作成致します)
(3)実名投稿のみです。
*盗難車情報の詳細は当社検索サイト(会員制)をご覧ください。
-----皆様からお知らせして頂いた最新盗難情報の掲載----- |